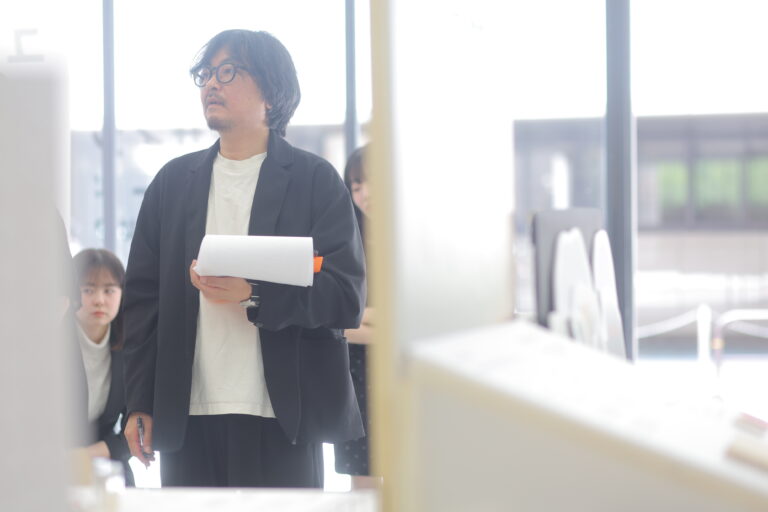【学生記事】歴史上の人物から習う「二刀流」

こんにちは、2年の小林です。 みなさんは、『二刀流』と聞いて思い浮かべる歴史上の人物は誰ですか? そうです。巌流島の戦いで佐々木小次郎と戦った日本一強い剣豪「宮本武蔵」です。ではなぜ、「宮本武蔵」は『二刀流』を使うのでしょうか? 本当の刀を持った方ならわかると思うのですが、実は結構重たく、約1kg~1.4kgもあります。 そんな重い刀を両手に持って振り回したりしていると、かなりの体力が必要でしょう。 宮本武蔵は相当な阿呆ということがわかります。
しかし、そんな『二刀流』には、 「戦闘中、どんな状況になるか分からないため、片手でも刀が振れるようにする」という意味があります。 相手が多い時は武器も多い方がいいし、1本の刀を両手で使っては多勢の攻撃にやられてしまいます。 もし、相手から攻撃を受けてしまい利き腕が使えない場合もありうるのです。 周りの武士たちは刀1本で戦いに来ているのに対して、状況で瞬時にスタイルを変える宮本武蔵はひと味違ったようです。 さて、剣豪「宮本武蔵」は剣術家でしたが、実は「五輪書」を書く兵法家であったり、 《枯木鳴鵙図》という水墨画を描く画家でもあったりします。
すごいですよね! 刀は二刀流だけど、職業は三刀流というハイスペック武士だったんです。 「私はイラストを描けます。」よりも、 「私はイラストも描けますし、webデザインも、写真、何から何まで得意です。」と周りと自分との差別化、 スタイルが変えられることで手に職をつけることができると思います。 私もこの御茶の水美術専門学校に入学してから、学ぶ時間が取れ、 何かを作ったり、書いたり、読んだりと入学前の自分と比べて、成長していると感じています。 「構えあって構えなし」 みなさんも臨機応変にスタイルが変えれる宮本武蔵のように自分から挑戦してみたり、学んでみたりしてください。
資料請求はこちら!
→ゼロワーク®プログラム
→デザインアート思考®
→ビジュアルコミュニケーション
→プロジェクトベースドラーニング
→御茶の水美術専門学校は、産学、官学連携授業実践校です
→交通と立地「在校生インタビュー」